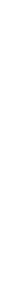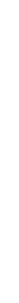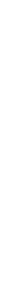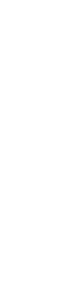桜の蕾が赤みを帯びる頃は、私たちのからだが上を向きたいと思う頃。その溢れんばかりの力強さを少しでも感じたくて、背筋が自ずと伸びるのは私だけでしょうか。ほころび、そして花が開きはじめると、からだも開いていく。花を愛でれば、少し前の愁いも次第に消え、活動的になっていく。桜の便りが北上するとともに、日本に住む人の気分も上昇しているとしたら、とても喜ばしいことです。


私たちは桜と、つながっている。1000年をはるかに超えて私たちが桜を想い続ける訳は、そこに植えられているから、というものではなく、四季とともに移り変わる私たちの心身と、四季とともに移り変わる桜の営みが、呼応しているからかもしれません。咲きはじめから散りゆくさまが人生に例えられるのも、もちろん一理。美しいだけではなく、生きている深みを共有できると感じているから、そこに桜を植えた。そうして、よりいっそう桜とつきあうことになってきたのではないでしょうか。若い頃は敢えて桜に背を向けていたと語る人もいますが、背を向けたくなるほどの存在感を持つ花を他に思い出せません。嬉しいとき、悲しいとき、どのような状況においても、意識せずにはいられないところも含め、日本の花と言われるのは当然のような気がします。
文学における「花」は、平安時代以降、「梅」から「桜」へ替わったとされています。花曇り、花冷え、花衣、花の雲、花の雨、花の宿、花の昼…、散った花が水に浮かぶことを、まるで筏のようだと見立て「花筏(はないかだ)」と呼ぶ。一床、二床と浮かぶ数少ない花筏には趣があります。何百床、何千床ともなれば、川をうねりながら織りなし、前衛的ともいえる芸術と化すことを、ある映像から知りました。先人たちは、日常に使う言葉に「花」を添えることで、短いひとときを十分に味わおうとしたのです。私は、その気持ちを受け継ぎ、また後世に残していけたらと願っています。
花が散りはじめると、同時に若葉が芽吹き、葉桜としての美しさを愛でることができます。その後、すべてが落花し、がくに残った紅い蘂(しべ)が目立ちはじめ、そして、「桜蘂降る(さくらしべふる)」。この言葉が晩春の季語として歳時記に掲載されています。蘂が音を立てて降り落ち、地面を覆いつ尽くすこともあります。そのさまを感慨深く思えるようになるには、どのような人生を歩めばよいのか。私の課題の一つになっています。


続いて、まぶしいきらめきに心が動く新緑の葉に満ちる頃となり、夏の茂りを迎え、秋が深まれば、紅く色づき、桜紅葉を見ながらの宴を催すこともできます。秋の気候のなかでの落ち着いた雰囲気を想像すると、花の宴よりも俗世間から離れるように思え、風流に感じます。

冬は、寒さに耐えることで、強く逞しく成長をします。樹齢1000年の巨木を見守る村では、雪の積もる枝を見た人たちが、「がんばりなさいよ。春はもうすぐだからね」と声をかけるそうです。そこまで想いを捧げられる人になれたら、日々の生活は潤うことでしょう。
桜が動きはじめようとするのは、私たちと同じく、一年のはじまりであるお正月を過ぎたあたりからのような気がします。桜が根に力を込め、私たちは大地をつかもうと足の裏に力を込める。立春になれば、暦通りに春めく陽射しを浴び、確かな心構えをする。そして、芽吹きます。樹木の内側をこっそりと覗けば、きっと想像を超えたものを目にすることができるのではないかと思い、ときどき木肌に触れているところは誰にも見られたくない楽しみです。

桜が最も上気立つときは、桜の花が開く直前と、中学二年生の国語の教科書に引用されている『言葉の力』から知りました。作者は、詩人で評論家の大岡信さん。その時期に染めた糸で織り上げた着物を目にして、「そのピンクは淡いようでいて、しかも燃えるような強さを内に秘め、はなやかで、しかも深く落ち着いている色だった。その美しさは目と心を吸い込むように感じられた」と。実は、花びらではなく、黒っぽい樹皮で染めたことを染色家から聞いた大岡さんは、からだが一瞬揺らぐような不思議な感覚に襲われたそうです。「春先、間もなく花となって咲き出でようとしている桜の木が、花びらだけでなく、木全体で懸命になって最上のピンクの色になろうとしている姿が、私の脳裡にゆらめいたからである。花びらのピンクは幹のピンクであり、樹皮のピンクであり、樹液のピンクであった。」
桜も、一年中、生きています。何事においても、華やかな時期や華やかなところだけ
に目を向けていると、大事なことを見落としてしまいそうになります。
そうならないためにも、春の桜だけではなく、夏の桜、秋の桜、冬の桜にも気持ちを向けたいと思っています。