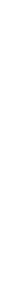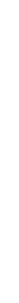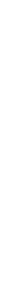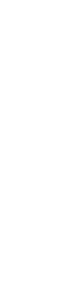人は、遥かむかし、土から作られ、生まれたと聞いたことがあります。そして、さいごは土へと還るということも。私が、人と土との関わりに想いを馳せることが多くなるのは、暦の上での春を迎え、土が匂いはじめる2月のことです。
その匂いは、春の陽気に誘われた農夫が、田の土を掘る「田起こし(田打ち)」という農作業をはじめたことにより漂ってくるものです。花のような華やかさはありませんが、薬に似た渋みに何故だか惹かれ、まるで春の身体が苦みを欲するように、長く匂っていたいという気持ちになります。その土を雨が降り包むと、より生き生きとした世界が目の前に広がり、すべてにおける春がやってきます。

田のまわりの土手や畔などに草の芽が萌えはじめるのも、このころ。土の中の活動に勢いが出てきたことを想像できます。私は、このような下萌(したもえ)を感じたとき、土の中にも春の光が作られていると思うことがあります。太陽とは異なる光を受けて植物は、まるで輝いているように生え出ずると。


ところで、旧暦には季節を表現するものとして「七十二候」というものがあります。一年を72等分し、草木や動物、虹や風といった気象などのうつりかわりを表すものです。最近ではこのような暦に親しむ人が増えていると聞きますが、区切りとともに自分を細かに見つめることで、こころの平穏を保つことができるからなのかもしれません。
2月18日から22日のころは、七十二候でいう「土脉潤起(つちのしょううるおいおこる)」。二十四節気でいうと、「雨水(うすい)」の時季にあたり、陽気が地上に発せられ、雨が降りやすくなるので、土が湿り気を帯びるころということになります。七十二候は、その通りに季節を感じられるかというと、必ずしもそうではありませんが、「土脉潤起」は現実と重なるひとつ。それゆえに、ますます躍動する土を想像せずにはいられなくなります。
土そのものに触れていなくても、土から顔を出す植物のことが七十二候では多く表わされています。たとえば、1月20日から24日のころは、冬の氷をやぶって蕗の薹(ふきのとう)が生えてくる「欸冬華(ふきのはなさく)」。このころになると、蕗の薹が恋しくなり、2月上旬にはみつけることができるので、摘んで素揚げにしていただきます。そして毎年、寒さのなかで踏ん張って力を蓄え、何が起ころうとも春の土をまとって自力で蘇る姿に励まされます。



このような土や土から生まれる生命の営みには、田園地帯でしか触れることができないと思われがちです。けれども、そうとも言い切れません。なぜなら、私たちが生活のために望むすべてのものは、土から生まれているといっても過言ではないからです。材料を考えながら想い浮かべられるものは、日々の飲食物はもちろんのこと、衣服、本、器…。私がこのことを聞いたときは、当たり前のことを忘れてしまっている自分に愕然としたものです。そして、私たちも土から生まれたという言い伝えが頭をよぎり、人と土との関わりに想いを馳せました。
七十二候からも知ることができる、多くのものが蘇り息づく春に、このような壮大な想いを巡らせてみる。さらに、土が匂えば、そぞろ歩き、蕗の薹が顔を出せば、味わい、自分のまわりにあるものを眺めては、生まれたよろこびを感じる。それは、とても大事なことなのかもしれません。