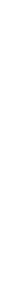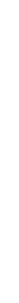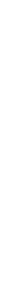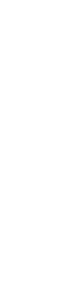胡瓜、トマト、茄子、苦瓜、オクラ、南瓜、ピーマン、紫蘇。これらは、田園地域に住む私が8月に毎日と言っていいほど口にしている野菜です。ありがたいことに、日々の野菜は、どの季節も旬のもののみ。我が家の畑で採れるもの、隣近所と交換するもの、そして町内で収穫し売られているもので十分に足りる生活をしています。
今の生活は子どもの頃とほとんど変わりませんが、ひとつひとつの野菜の、その季節に食べ初める嬉しさと終える寂しさは大人になってから知りました。限られた者だけが味わえる感情といえるでしょうか。特に、夏野菜の、今日で最後という日の寂しさは、他の季節よりもひとしお。濃い色や瑞々しさ、歯ごたえで魅了する種類が多いからか、暑さにより疲労した心身を支えてくれたからか。その気持ちは、夏から秋へと向かう日暮れどきのせつなさと似ています。

このような日々の経験に加え、都心などでさまざまな料理を食べ歩いた経験を持つことから、私は胸を張って「一番の美食は、おいしい野菜である」と言うことができます。“おいしい”は、鮮度の高さに左右されるもの。収穫後すぐ口にすると、瑞々しさや香り、力強さ、さらにはじんわりと伝わる甘さに目を見開き、しみじみ「おいしい」ともらします。それは、複雑な料理からは味わえない悦びです。
人間の身体と暮らす土地とは切り離せない関係にあり、その土地でその季節に採れたものを食べると健康である。このような考えが「身土不二(しんどふじ)」の四文字で表わされていますが、私の身体は頭よりも、この考えをはるかに理解しているような気がしています。


随筆家で食通としても知られていた白洲正子さんの著書『日本のたくみ』(新潮文庫)のなかに、日本の料理の鮮度や旬について述べられている頁があります。日本の料理は、「魚や野菜が本来持っている味を、いわば内部からひきだすことにかかっているように思われる。材料が新鮮なら、醤油と塩で喰べるに越したことはない」と。新鮮な食材をいただくのであれば、「人間にできることは、ほんのちょっと手を貸してやるだけにすぎない」とも。そのため、「日本には料理がない」といわれているそうです。もちろん、悪い意味ではありません。「たしかに私たちの国では、外国のような調理法は発達しなかった。海の幸、山の幸に、恵まれすぎていたからだ。そこに彼らとはまったく別な味わい方が生れた。四季折々のシュンを尊ぶこと、包丁さばきから器のえらび方、その盛りつけに至るまで、自然の味を生かすことに細心の注意がはらわれる」。今もなお、尊ぶに値する四季折々の豊かな恵みを持つ日本です。そうであるのに、「シュンの有がたみ」が忘れられている現代を著者は嘆いています。私たちは、旬以外の食を、どうして求めてしまうようになったのでしょうか。
私の住むまちのように田園が多い地域では、8月は、夏野菜の実りとともに、稲の最も大事で急速な成長を目にすることのできるひと月でもあります。炎天に向かって青々と伸びる稲に穂がつき、小さな白い花が咲き、もみが膨らみ、稲穂が垂れ、いよいよ黄金へと色づく。稲作がはじまったとされる縄文時代から続いてきたであろう真夏から初秋への光景が広がります。


その季節の新鮮な野菜と、日本に住むものの命をつないできた米。残暑のなか、目の前で輝きを放つ恵みを見つめていると、これらを尊び、これらを中心とする日々の食事を、どこに居ても大切にしていきたいと強く思います。